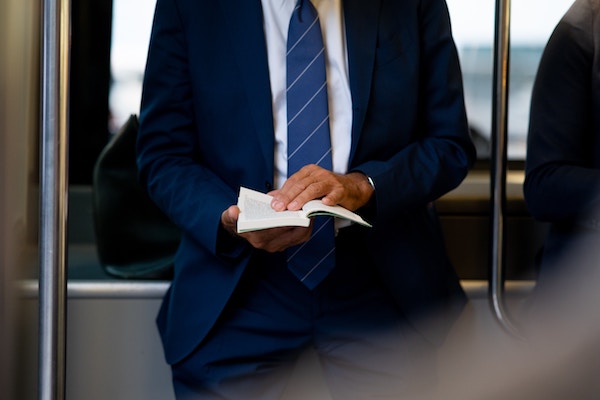
この記事は「現在営業マンをやっているけど、なかなか契約が取れなくて悩んでいる」という方に向けて書いています。
世の中にはたくさんの営業マンが日々頑張って営業活動をしています。しかし、現実には契約が取れる人と取れない人が存在します。
契約が取れる営業マンにはさまざまな共通点がありますが、今回はその中でも飛び道具的な方法として「営業マンをほかの名前に言い換える」というテクニックを紹介します。
目次
営業マンを言い換えると契約率が上がる理由|ほかの呼び方を紹介

どの会社にも、契約がとれる営業マンと、まったく契約がとれない営業マンが存在します。
イタリアの経済学者が発見したパレートの法則では「80:20」というものがあり、これは上位20%の優秀な社員が会社全体の80%の売上をつくっているという内容です。
つまり、会社組織の中には、たったの20%しか契約がとれる営業マンは存在しないということになります。
たいていの人は80%の普通以下の営業マンになるので、20%のできる営業マンの中に入るためには、普通の人がやっているのと同じ方法で営業していてはダメだということです。
先ほど、契約がとれる営業マンになるためのテクニックとして「営業マンをほかの名前に言い換える」という話をしました。
結論を言うと、これはとても簡単な手法ですが、効果は絶大です。
「ただの営業マンではない特別な存在」になることが重要です。
「営業マン=商品を売りつける人」というイメージが強い
世間では、「営業マン=商品を売りつける人」というイメージを持っている人がかなり多いです。
営業マンは、売って終わり、ただ売るだけの人、というようなネガティブイメージが強いということです。
これは会社から課せられた売上目標を必死で達成しようとする営業マンたちが、倫理を無視した最低な売り方をしてきた結果、営業マンの印象が悪くなっているのです。
さらに、誰でもそうだと思いますが、売りつけられることや営業されることって、なんか嫌ですよね?
営業マンをするうえでは、このお客様の心理を理解しておかないといけません。
営業マンと聞くと多くの人は身構える
「営業マン=売りつける人」という印象があるので、多くの人は営業マンと聞くだけで身構えます。
「何か質問をしたら、めちゃくちゃ営業されるのではないか?」
「少しでも興味がある雰囲気を出したら、契約しなきゃいけないのではないか?」
このような恐怖があり、営業マンに対して強い警戒心をもつ人はたくさんいます。
たとえば、知り合いから「保険の営業をやっている」「ネットワークビジネスを始めた」などと聞くと、ちょっと距離をおきたくなりますよね?
これと同じ心理状態が、営業マンとお客様の間にも起こっているということです。
ですから、営業マンというだけで、お客様は身構えて、なかなか本音を言ってくれないこともあります。
本質的なお客様の困りごとや課題がヒアリングできず、結果的に的外れな提案となり、失注になってしまうのです。
お客様の営業マンに対してのガードをいかに下げられるかが、契約を取るためには大切だということです。
その一つの方法が「営業マンを言い換える」ということですね。
営業マンを言い換えた呼び方を紹介

では、営業マンを言い換えた呼び方には、どのようなものがあるのでしょうか?
以下に、呼び方の例をいくつか紹介しますね。
- 営業担当
- 担当者
- 仲介人
- 販売スタッフ
- 販売担当
- カリスマ販売員
- 販促員
- 外交員
- 外勤社員
- PR担当
- カリスマ販売員
- 販促員
- ビジネスマン
- セールスマン
- ブローカー
- ディーラー
- アカウントエグゼクティブ
- サービスマネージャー
- アカウントマネージャー
- コンタクトマン
- サービスマネージャー
- セールスレプリゼンタティブ
- セールススタッフ
- コンサルタント
- プランナー
- コーディネーター
- サポーター
上記のとおり。
本当は全て営業マンのことですが、こうやって呼び方を変えると営業マンっぽさが緩和されますよね?
最近は名刺にも「営業」ではなく、横文字の名前を記載している会社も増えてきています。
本当にちょっとしたことですが、営業マンの肩書きを言い換えるだけで、お客様が営業マンを見る目は変わります。
それだけ人間は、肩書きに影響されやすいというこですね。
お客様がどんな人のアドバイスなら素直に聞くか考える
「営業マンを言い換える呼び方がいろいろあるのは分かったけど、結局どの肩書を選べばいいの?」
このように思った方もいますよね。
どの肩書を選ぶかの前に、お客様が「どんな人のアドバイスなら素直に耳を傾けるか?」を考えることが重要です。
営業マンが相手では身構えてしまって本音を言ってくれない。じゃあ「誰に対してなら本音を言ってくれそうか?」を考えるのです。
商品企画担当者、システム開発者、税理士、経営コンサルタント、専門家など。
お客様には「その人の話なら素直に聞ける」という相手が、必ず存在します。
その人物を想像して、自分をそこに近づけることができれば、お客様は本音を言ってくれやすくなります。
本音を引き出せれば、困りごとや課題に対しての提案の精度が高くなるので、契約率も高くなります。
営業マンの言い換えで1番良いのはコンサルタント

これは私の経験上ですが、営業マンの言い換えで1番効果的なのは「コンサルタント」でした。
「経営コンサルタント」や「業界のコンサルタント」のような、企業に対してアドバイスをするようなポジションの肩書きですね。
「コンサルタント」というのは、特別な資格や経験がなくても、誰でも名乗ることができる肩書きです。
世の中にはいろいろな種類のコンサルタントがいます。経営コンサルタント、営業コンサルタント、採用コンサルタント、システムコンサルタント、WEBコンサルタント、組織コンサルタントなど。
コンサルタントという肩書きは、具体的にどんな仕事をしているかが曖昧なので、「よくわからないけど、なんかすごい人。何でも知っている人」という印象をお客様に与えやすいです。
コンサルタントは、お客様の課題を見つけたり、課題を解決するためのアドバイスをするのが主な業務になるので、売るだけの営業マンとはまったく違うポジションをとることができます。
客観的な視点からお客様にアドバイスをし、その中で自分が販売したい商品も織り交ぜて提案していく、というスタイルで営業をしていると、お客様からの信頼がものすごく高くなり、契約率も飛躍的に伸びていきます。
当然、コンサルタントと名乗るわけですから、自社商品はもちろん、業界の動向や他業界のトレンドなども常に勉強して、自分の知識をアップデートし続けることは必要ですけどね。
私自身も営業マンとして営業していた頃よりも、コンサルタントとして営業をし始めたあとの方が契約率は高くなりました。1.5~2倍くらいは契約率が上がったと思います。
さらに、コンサルタントと名乗るようになってから読書量や勉強量が多くなったので、契約率上昇にはそれも影響していると思いますね。
コンサルタントになるとセミナー依頼や紹介が増える
コンサルタントとして営業するようになると、「売るだけのただの営業マン」という立ち位置から「アドバイスをしてくれる先生」のような立ち位置に変わっていきます。
それによって、お客様から相談の連絡が頻繁にくるようになるので、その度にお客様の困りごとや課題を確認することができ、追加の提案のチャンスを獲得することができます。
商談の回数が増えれば、契約数も増えるので、好循環で営業活動を続けていくことができるようになります。
さらに先生という立場になるので、セミナーや勉強会の依頼も増えていきます。
「今度協会の会合があるから、そこでセミナーをやってくれないか?」
「従業員を集めて勉強会がやりたいので来てくれないか?」
上記のように、講師としての仕事も増えていきます。
講師としての仕事をしていると勝手に信用度が高くなっていくので、お客様から新しいお客様を紹介していただくことも増えていきます。
紹介からの商談の契約率は80%以上はあるので、さらに好循環で仕事がまわっていきます。
私自身が「コンサルタント」と名乗って営業するようになってから、セミナー講師をやったり、勉強会の講師をやったり、紹介からの受注が増えたりしていきました。
ですから「営業マンをコンサルタントに言い換える」を試してみるのも良いかと思います。
【関連記事】
⇒営業で売れない新人が契約450件とる方法【失敗談あり】


